
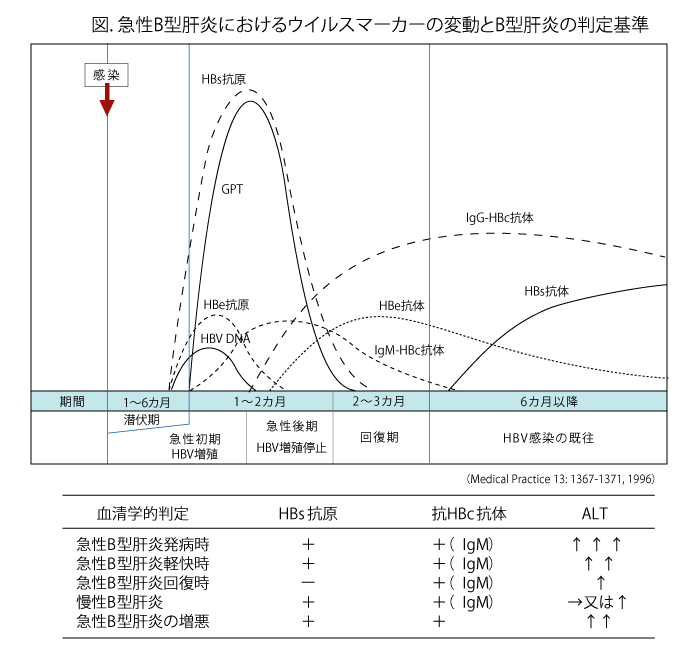
血液検査では、まずHBs抗原を検査します。検査でHBs抗原が検出された場合、その人の肝臓の中でHBVが増殖しており、また、血液の中にHBVが存在するということを意味します。
HBVは、直径42nm(ナノメーター:1nmは1mの10億分の1の長さ)の球形をしたDNA型ウイルスで、ヘパドナ(ヘパ:肝、ドナ:DNA、つまり肝臓に病気を起こすDNA型のウイルスという意味)ウイルス科に属します.
ウイルス粒子は二重構造をしており、ウイルスDNAをヌクレオカプシド(nucleocapsid)が包む直径約27nmのコア粒子と、これを被う外殻(エンベロープ、envelope)から成り立っています。
HBV粒子の外殻を構成するタンパクがHBs抗原タンパクであり、コア粒子の表面を構成するタンパクがHBc抗原タンパクです。
HBe抗原は、HBVの芯(コア粒子)の一部を構成するタンパクですが、HBVに感染した人の肝細胞の中で増殖する際に過剰に作られて、HBVのコア粒子を構成するタンパクとは別個に、可溶性の(粒子を形成しない)タンパクとしても大量に血液中に流れ出します。
一般の検査で検出されるHBe抗原は、HBVのコア粒子を構成するHBe抗原タンパクではなく、血液中に流れ出した可溶性のHBe抗原タンパクです。
HBe抗原タンパクは、感染した肝細胞内でHBVが盛んに増殖している間は過剰に作られ、血液中にも流れ出しますが、HBVの遺伝子の一部が変異すると、血液中へ流れ出す形での可溶性のHBe抗原タンパクは作られなくなります。このような状態になると、血液中のHBe抗原は検出されなくなり、代ってHBe抗体が検出されるようになります。一般に、このような状態になると、肝細胞の中でのHBVの増殖もおだやかになります。
HBs抗体は、HBV粒子の外殻、小型球形粒子、桿状粒子(HBs抗原)に対する抗体です。一過性にHBVに感染した場合、HBs抗体は、HBs抗原が血液の中から消えた後に遅れて血中に出現します。
一般に、HBs抗体はHBVの感染を防御する働き(中和抗体としての働き)を持っています。
HBc抗原は、HBVの芯(コア粒子)を構成するタンパクですが、外殻(エンベロープ)に包まれてHBV粒子の内部に存在することから、そのままでは検出できません。近年、検体に特殊な処理をほどこし、HBV粒子全体をバラバラに破壊することにより、HBVのコア粒子を構成するタンパク(ペプチド)を検出する試みが行われています。この方法で検査すると、HBVのコア粒子を構成するHBc抗原とHBe抗原の両者が同時に検出されることが明らかになってきました。近い将来、この抗原を検出、定量する方法が日常検査の中に取り入れられれば、HBVキャリアの血液中のウイルス量を簡便に知ることや、感染した肝細胞の中でのウイルス増殖の状態を知ること、さらにはB型肝炎に対する抗ウイルス療法の効果を評価する際などに活用できることが期待されます
。HBVに一過性に感染すると、HBc抗体は、HBs抗原が血液中から消える前の早い段階から出現します。まずIgM型のHBc抗体が出現し、これは数ヶ月で消えます。IgG型のHBc抗体は、IgM型のHBc抗体に少し遅れて出現します。このようにして作られたHBc抗体は、ほぼ生涯にわたって血中に持続して検出されます。
HBe抗原は、HBVの芯(コア粒子)の一部を構成するタンパクですが、可溶性の(粒子を形成しない)タンパクとしても血中に存在することが知られています。
一般に、検査室で検出されるHBe抗原は、感染した肝細胞の中でHBVが増殖する際に過剰に作られ、HBV粒子の芯(コア粒子)を構成するタンパクとは別個に血液中に流れ出した可溶性のタンパクであることがわかっています。
血液中のHBe抗原が陽性ということは、その人の肝臓の中でHBVが盛んに増殖していることを意味します。言いかえれば、HBe抗原が陽性のHBVキャリアの血液の中には、HBVの量が多く、感染性が高いことを意味します。
HBe抗体はHBe抗原に対する抗体です。HBe抗体にはHBVの感染を防御する働き(中和抗体としての働き)はありません。
HBVキャリアは、小児期にはHBe抗原陽性ですが、多くの人では10歳代から30歳代にかけてHBe抗原陽性の状態からHBe抗体陽性の状態へ変化し、これを契機に、ほとんどの人では肝炎の活動も沈静化することがわかっています.
核酸増幅検査(Nucleic acid Amplification Test:NAT)とは、標的とする遺伝子の一部を試験管内で約1億倍に増やして検出する方法で、基本的には、PCR(Polymerase chain reaction)と呼ばれていたものと同じ検査法です。
この方法をHBVの検出に応用すると、血液(検体)中のごく微量のHBVの遺伝子を感度よく検出することができます。このことから、NATによるHBV DNA検査をスクリーニングに応用して、HBVに感染して間もないために、HBs抗原がまだ検出されない時期(HBs抗原のウィンドウ期)にあたる人を見つけ出したり、HBs抗原が陰性でHBc抗体だけが陽性である人の中から、現在HBVに「感染している」人を見つけ出すことにより、輸血用血液の安全性の向上のために役立てられています.
「感染後どのくらいの期間が経てば、HBs抗原検査でウイルスに感染したことがわかりますか? 」
HBs抗原検査法の感度にもよりますが、ヒトでの解析結果をもとにした外国からの報告によれば、感染後約59日経てばHBs抗原検査でウイルスに感染したことがわかるとされています(Shreiber G B他、N. Engl. J. Med. 1996)。
「感染後どのくらいの期間が経てば、B型肝炎ウイルス遺伝子(HBV DNA)検査でウイルスに感染していることがわかりますか? 」
ヒトでの解析結果をもとにした外国からの報告によれば、感染後、約34日経てばHBV DNA検査でウイルスに感染したことがわかるとされています。
「血液検査でB型肝炎ウイルス(HBV)に感染していることがわかったら、どうしたらよいですか? 」
急性肝炎を発病し、その原因ウイルスを調べるために受けた検査でHBs抗原が陽性である(HBVに感染している)ことがわかった人を除けば、献血時や検診時の検査で偶然HBs抗原が陽性であることがわかった人のほとんどはHBVキャリアであると考えられます。HBVの急性感染かHBVキャリアかは、IgM型HBc抗体検査(急性感染では陽性、HBVキャリアの多くは陰性を示す)やHBc抗体力価の測定(一般にHBVキャリアでは高力価を示す)、またはHBs抗原量やHBc抗体価の推移を追うことなどにより鑑別することができます。
0 件のコメント:
コメントを投稿